卒業論文から学ぶ
片桐由喜 (小樽商科大学商学部 教授)
理系のことは、わからないけれど、文系に関して言えば、卒論が卒業に必須であるかどうかは大学によって異なる。つまり、各大学各学部が自由に決めている。大学受験をするときに、卒業論文が必須か否かまで確認する受験生はあまりいないだろうから、入学して初めて「えっ、あるの?」、「わっ、なくてよかった」などなど、思うことは様々である。
本学は卒論必須である。学生も大変だが、読んで添削して、褒めて叱ってと教師はもっと大変である。それでも、学生の成長を実感することができて教師みょうりに尽きる。なにより、5本に1本(10本に1本か?)は学生の書いた卒論から学ぶことがある。
このような卒論の特徴は2つある。1つは、学生自身が足を使って調べ、直接、関係者から話を聞いて書くタイプの論文である。私の知らないことが豊富な実例とともに書かれていて、新たな発見に満ちている。読んでいて心地よい卒論である。加えて、このような卒論はコピペ論文の対極にあり、読んでいてストレスがない。
もう1つは、自らの強烈な問題関心に基づいて書く場合である。これは当該問題の当事者である場合もあれば、そうでない場合もある。当事者性よりも、どれだけそのテーマに対して熱い思いを持っているかが重要である。
今年、上記2つの性格を備えた卒論を1つ、紹介する。これは自分の親が病に倒れ、入院から障害者支援サービスを利用するまで間、種々の公的給付を受けるに際し、役所でたらい回しにされ、関係事業所担当者の不正確な情報と知識に振り回された経験がテーマ選択の動機となった卒論である。
私たち研究者は、ときに知った風な顔で縦割り行政や、不親切な役所担当者を批判する。これは自らの経験に基づくというよりは、役所に対するステレオタイプなイメージ、公然の事実であるとの認識に基づいている。実際にたらい回しにされたわけではないので、その主張は上っ面を撫でる域を越えず、この種の批判はいわば「枕詞」のようなものである。
しかし、今回、当該学生は自分と家族が直面した様々な困難を克服するために役所を回り、奔走した日々の中で実際に感じた憤り、あきらめ、落胆に基づいて書いた。そのため説得力ある文章になっている。そして、卒論の中で他地域の好事例を紹介しながら、市民、とりわけ弱者となった市民に寄り添うためにどのような体制、システムが必要であるかを自ら考えて締めくくる。
学生自身が疑問に思い、批判的に考える社会の事象を客観的な事実と自らの体験に基づいて、その背景と解決策を書く機会を卒論が与えた。おそらく、就職後には自分がおかしいと思うことをそれなりに長い文章にして書く機会は、そうないはずである。こういうところに卒論の意義があるのだろう。
毎年、卒論必須制度を廃止してほしいと願うのだけれど、こういう卒論に接すると、存続やむなしと思い至る。
下の写真は当ゼミで毎年、独自に作成している卒論集である。学生たちや、彼らの後輩たちは前半の卒論よりも、後半のページに綴られている「プロフィール」、「思い出の写真コーナーを熟読。それもよしである。
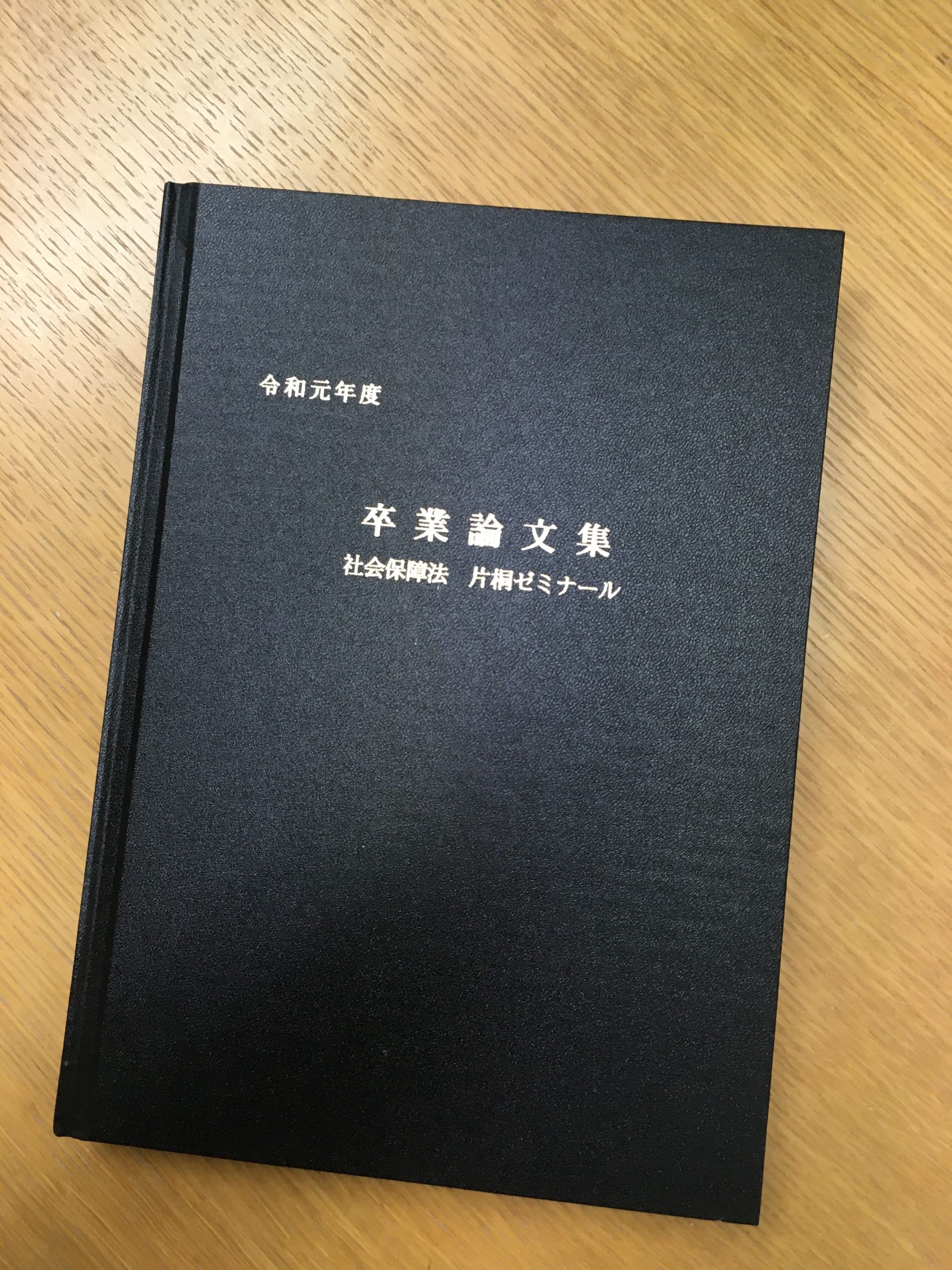
ーー
片桐由喜(小樽商科大学商学部 教授)
◇◇片桐氏の掲載済コラム◇◇
◆「オンライン授業と遠距離通学」【2020年10月27日掲載】
◆「オンライン授業強行記」【2020年6月23日掲載】
◆「雪あかりの路に思う」【2020年2月25日掲載】
☞それ以前のコラムはこちらからご覧ください。

